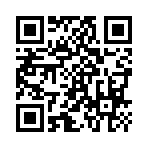› 江戸屋 › インクルージョン成功
› 江戸屋 › インクルージョン成功2024年09月28日
インクルージョン成功
9月で次年度のクラスを支援級にするか?通常級にするか?悩むところです。
半年後の子供の様子がわかるわけがないので、もう少しギリギリに決定できたら良いですが、学校も教員不足で支援級担当の先生を確保するのに苦労しているそうです。
それでも学校から支援級を強く勧められる利用者も居たり、様々です。
今月は、2人の利用者が次年度のクラスをどうするか?で学校や病院のかかりつけ医と会議を行い、2人共、次年度は通常級で学校生活を送る事に決定しました。
昨年も同様の相談が保護者からあり、
「学校は支援級を勧めているのですが、通常級に入りたいと子供が言ってるので、先生との面談に同席して欲しい」と保護者から要望があり、「今、支援級を出て学ぶ機会だと思う」
と、学校に強く訴え、今年度から支援級を出て、通常級に入っていますが、特に問題は起きていません。
そして最も大事な事は
「試練の年となる」という事を保護者に理解して頂く事です。子供同士のもめ事も、先生から怒られる事も全ては、その子の為に必要な試練であり、それを乗り越えて行かなければ、社会では通用しないという事を十分、理解して子離れしてもらう事です。
支援級から通常級へと狭い世界ですが、インクルージョン成功だと思っています。
上記の3名はIQが元々高く、一名は今年の発達検査で、IQ113に爆上がりしていた事もあり、学習面では問題なし。
情緒面では、支援級から出るにあたり、利用者には如何に上手くやって行くかを話し、問題のある言動があれば、利用者を呼び、
「ちょっと座って。今の発言、嫌われるという事に気づいてる?」など、きめ細かく指導します。
放課後等デイサービスの活動室が広すぎるのはダメだと、オープンする時に聞いています。
広い活動スペースでは、子供ひとりひとりの様子が見えませんし、ただ遊ばせて発散させるだけでは療育とは言えません。
先日の学校での会議でも、校長、教頭、教育コーディネーター、教育委員会、支援級担任、交流級担任、スクールソーシャルワーカーが参加する沢山の方の意見、学校の状況をお聞きしましたが、あっちでもこっちでもトラブルが多く、児童や保護者を呼んで話し合いを行っていると、児童の対応に追われていると漏らしていました。
その中で、
「どうやって正しい事を教えるか?が難しい」と仰るので、社会性は大元に認知の歪みがある事が原因で、実際にアニマート内で実験を行った結果などを説明して来ました。
「友達を叩いてはいけません」と見えている行動を注意するだけでは、やった本人には様々な理由があり、一方的に怒って、正しい事を教えるだけでは、子供は納得しないですし、何故いけないのかもわかっていない事があります。だから何度も同じ様な事で怒られる。
最近では、学校との会議で発言すると、先生方が一生懸命、メモを取りながら、真剣に耳を傾けてくれる事が多いです。これまで10年以上、支援に関わって、日本だけでなく、海外の研究を読み漁り、獲得して来た知識。学校、保護者と私達事業所での連携が非常に取りやすくなっています。今週、行った学校も初めての会議でしたが、快く受け入れて下さった事に感謝致します。
次年度、支援級を出る児童、生徒は、これで終わりではありません。
あと半年で、どれだけ気持ちを整えて準備して行くかです。
個別支援計画書も、一気にハードルが上がるかもしせませんが、将来、親が居なくなった後も自分で自立する為には、試練が必要です。
子供に試練を与える事を拒む保護者も居ますが、人生、どこかで頑張らなきゃいけない時が来ます。
それが、この本にも書かれているので、神経発達症(発達障害)を持つ保護者の方には、是非読んで頂きたい。
↓
「どうしても頑張れない人たち~ケーキの切れない非行少年たち2 」
アニマート江戸屋は、障害児の支援に関わって、最長で13年、10年、8年、7年・・・と経験豊富な指導員がおります。
半年後の子供の様子がわかるわけがないので、もう少しギリギリに決定できたら良いですが、学校も教員不足で支援級担当の先生を確保するのに苦労しているそうです。
それでも学校から支援級を強く勧められる利用者も居たり、様々です。
今月は、2人の利用者が次年度のクラスをどうするか?で学校や病院のかかりつけ医と会議を行い、2人共、次年度は通常級で学校生活を送る事に決定しました。
昨年も同様の相談が保護者からあり、
「学校は支援級を勧めているのですが、通常級に入りたいと子供が言ってるので、先生との面談に同席して欲しい」と保護者から要望があり、「今、支援級を出て学ぶ機会だと思う」
と、学校に強く訴え、今年度から支援級を出て、通常級に入っていますが、特に問題は起きていません。
そして最も大事な事は
「試練の年となる」という事を保護者に理解して頂く事です。子供同士のもめ事も、先生から怒られる事も全ては、その子の為に必要な試練であり、それを乗り越えて行かなければ、社会では通用しないという事を十分、理解して子離れしてもらう事です。
支援級から通常級へと狭い世界ですが、インクルージョン成功だと思っています。
上記の3名はIQが元々高く、一名は今年の発達検査で、IQ113に爆上がりしていた事もあり、学習面では問題なし。
情緒面では、支援級から出るにあたり、利用者には如何に上手くやって行くかを話し、問題のある言動があれば、利用者を呼び、
「ちょっと座って。今の発言、嫌われるという事に気づいてる?」など、きめ細かく指導します。
放課後等デイサービスの活動室が広すぎるのはダメだと、オープンする時に聞いています。
広い活動スペースでは、子供ひとりひとりの様子が見えませんし、ただ遊ばせて発散させるだけでは療育とは言えません。
先日の学校での会議でも、校長、教頭、教育コーディネーター、教育委員会、支援級担任、交流級担任、スクールソーシャルワーカーが参加する沢山の方の意見、学校の状況をお聞きしましたが、あっちでもこっちでもトラブルが多く、児童や保護者を呼んで話し合いを行っていると、児童の対応に追われていると漏らしていました。
その中で、
「どうやって正しい事を教えるか?が難しい」と仰るので、社会性は大元に認知の歪みがある事が原因で、実際にアニマート内で実験を行った結果などを説明して来ました。
「友達を叩いてはいけません」と見えている行動を注意するだけでは、やった本人には様々な理由があり、一方的に怒って、正しい事を教えるだけでは、子供は納得しないですし、何故いけないのかもわかっていない事があります。だから何度も同じ様な事で怒られる。
最近では、学校との会議で発言すると、先生方が一生懸命、メモを取りながら、真剣に耳を傾けてくれる事が多いです。これまで10年以上、支援に関わって、日本だけでなく、海外の研究を読み漁り、獲得して来た知識。学校、保護者と私達事業所での連携が非常に取りやすくなっています。今週、行った学校も初めての会議でしたが、快く受け入れて下さった事に感謝致します。
次年度、支援級を出る児童、生徒は、これで終わりではありません。
あと半年で、どれだけ気持ちを整えて準備して行くかです。
個別支援計画書も、一気にハードルが上がるかもしせませんが、将来、親が居なくなった後も自分で自立する為には、試練が必要です。
子供に試練を与える事を拒む保護者も居ますが、人生、どこかで頑張らなきゃいけない時が来ます。
それが、この本にも書かれているので、神経発達症(発達障害)を持つ保護者の方には、是非読んで頂きたい。
↓
「どうしても頑張れない人たち~ケーキの切れない非行少年たち2 」
アニマート江戸屋は、障害児の支援に関わって、最長で13年、10年、8年、7年・・・と経験豊富な指導員がおります。
Posted by 株式会社 江戸屋 at 17:00│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。